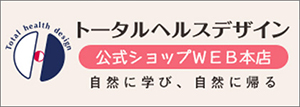研磨剤は、その名の通りエナメル質を削りながら磨く成分です。一度に大きな研磨が起こるわけではありませんが、長年使用を続けることで、知覚過敏を引き起こすレベルまでエナメル質が削れてしまうことがあります。実際の研磨の影響は医療機関でもタイムリーな確認が出来ないため注意が必要です。
一方、エナメル質の表面には電子顕微鏡で見ると小さな凹凸やクラックがあり、そこに虫歯菌やプラークが付着しやすいことが分かっています。そのため、エナメル質を保護するためには、表面をコーティングしてなだらかにするほうが丈夫になるという論文があると、知人の歯科医師から聞いたことがあります。
実は、バイオペーストを開発する前に、欧米で普及するイギリス製の車のコーティング剤の販売をしていた時期があります。高級車、船舶、航空機のコーティング剤ブランドで、ボディー表面の研磨やコーティングについて学んだ経験がありました。車の研磨剤には粒度や硬さに段階があり、徐々に細かいものに変えていくことで表面を滑らかに仕上げていきます。歯と違う点は、車の場合LEDやハロゲンライトを使って反射させることで、コーティングの状態を目視で確認できます。ロールスロイスやベントレーなどの高級車に対し、緊張感を持って肉眼でコーティングの仕上がりを確認するため、研磨剤や仕上げのコーティング剤がどの程度表面に影響しているのかを把握して作業を行います。また、しっかりとコーティングを施したボディーは汚れが付きにくく、長持ちしやすくなります。
 歯のエナメル質と車のボディーは異なるものですが、この経験がどこか感覚的に役に立っているように感じています。
歯のエナメル質と車のボディーは異なるものですが、この経験がどこか感覚的に役に立っているように感じています。
バイオペーストは、研磨をせず、穏やかなコーティング効果を狙った成分設計を行っています。そのため、成分についての詳細な調査を重ねてきました。
歯磨き剤に使用される研磨剤には、炭酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、ピロリン酸カルシウム、水酸化アルミニウム、酸化アルミニウム、シリカ、炭酸水素ナトリウム(重曹)、ゼオライトなどさまざまな種類があり化粧箱に記載が義務付けられています。しかし、一つの名称の中にも複数のメーカーや異なる種類が存在し、それぞれ粒度や硬さ、配合の目的や量が異なるため、化粧箱に記載された名称だけで研磨剤の影響を判断することは難しいのが現実です。化粧箱の記載を見て製品の評価をしている場面を目にしますが、開発側からすると、原料名で判断することは不可能です。
バイオペーストには「含水シリカ」が配合されていますが、これは歯のエナメル質よりも硬度が低く、粒子も非常に細かい種類のものを極少量配合しています。研磨効果はなく、歯の表面を優しく研磨し保護する目的で配合しています。また、重曹も含まれていますが、完全に水に溶かしイオン化してから配合しているため、研磨作用は全くなく、洗浄力のみが機能するようになっています。
歯磨き剤の研磨作用とコーティング効果は、それぞれの製品の設計や目的によって異なります。研磨剤の有無やコーティングの効果が気になる場合は、販売店やメーカーに詳細を確認することをおすすめします。
こうして調整されたバイオペーストは、最終的には知覚過敏の部位をしっかりと磨き続け、「それでも自然治癒が起きているか」で、検証もしています。