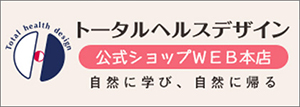私自身の体験談として、バイオペーストを開発したのは2016年頃ですが、それ以前は極度の知覚過敏症に悩まされていました。本当にひどく、何を食べても歯にしみる状態で、見る夢の半分以上が歯が抜け落ちる怖い夢。そのたびに夜中に飛び起き、洗面所の鏡に駆け寄るという毎日を過ごしていました。
もともと幼少の頃から母の躾が厳しく、勉強よりも歯を大切にすることを強く言われて育ちました。歯を磨かずに寝てしまうとたたき起こされ、幼いながらに歯磨きだけは怠らない習慣が身についていました。ズルをしようと、歯磨き剤を口に入れて飲み込み、親の臭いチェックを逃れようとしたこともありましたが、毎回胃が痛くなる経験をしたことで、「歯磨き剤は食べるものではない」と身をもって学んだこともよく覚えています。
中学三年生の頃、全校生徒を対象とした歯科検診があり、その後の朝礼で「名古屋市健康優良児(歯科)」として唯一表彰されたことがありました。それをきっかけに、「歯だけは守ろう」と心に誓いました。
その後もスルメや固いせんべいを問題なく食べられていましたが、今から20年ほど前、前述の知覚過敏症を発症し、日常生活に支障をきたすほどの苦痛を感じるようになったのです。

そんな中でチベット医学との出会いがあり、それをきっかけにバイオペーストを開発しました。自分で使い続けるうちに、いつの間にか知覚過敏の症状が完全になくなっていることに気づきました。また、販売当初から使用した知人たちからも同じような体験談が寄せられ、その後、知覚過敏の原因や治癒のメカニズムについて詳しく調べるようになりました。さらに、歯科医師とのディスカッションを重ね、バイオペーストの改良を続けてきました。
自身の経験から導き出した考えになりますが、唾液中のリン酸やカルシウムによって再石灰化されたエナメル質は、もともと歯を覆っていたエナメル質よりも酸には弱いようです。一度でも酸性の強い食品を長時間食べたり、食事の最後に摂取したりすると、翌朝には知覚過敏が再発します。そして、そこから適切なケアを行い、自然治癒させるという生活を繰り返しています。
しかし、様々な経験を通じて、どのようなケアが自然治癒に有効なのか、また食生活の習慣がいかに重要かを自ら検証することができました。
すし屋のガリ、弁当の梅干しは最後に食べない。食べたならお茶かビールで軽くすすぐ、果実の種は直ちに爪楊枝で除去する。レモン酎ハイも喉に直接流す。漬物はダラダラ食べない。などです。
また、これらの教訓は、バイオペーストの改良やマウスケアウォーターの商品化にも、大きな学びがありました。
歯は一度削ったり被せたりすると、隙間から虫歯が再発し、最終的には神経を抜いたり、抜歯をすることになるケースが多いのです。そのため、最初の「削る」という選択をできる限り避け、自然治癒で持ちこたえることが重要です。
ときには、貝などに入っていた小石によって歯が欠けてしまうこともあります。白米を噛むのも辛いほどの鋭い痛みがあったとしても、これまでの経験から学んだ正しいケアを実践することで、やがて醤油せんべいをバリバリと音を立てて食べられるようになる場合があります。
自然治癒を促す生活習慣を、ぜひ多くの方に知っていただきたい。
その強い思いを胸に、日々の活動を続けています。