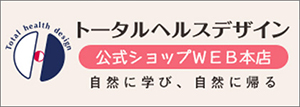歯学では、唾液中のリン酸やカルシウムにはエナメル質を再石灰化させる効果があるとされています。しかし、多くの市販の歯磨き剤には研磨剤が含まれており、エナメル質が削られる可能性もあります。
知覚過敏が自然に治癒することが実感されにくい理由のひとつは、研磨の影響がどの程度あるのかが明確でないためです。歯磨き剤の種類や磨く際の力の入れ方、歯ブラシの硬さといったさまざまな要素が影響し合い、結果として知覚過敏の改善が実感しにくいのが現状のようです。
歯磨き剤に含まれるフッ素濃度は1000~1500 ppmと高濃度です。一方、唾液中のリン酸やカルシウムの濃度には個人差がありますが、カルシウムは約30~70 ppm、リン酸は約30~100 ppm程度で、合計でも60~170 ppm程度になります。フッ素と比較するとかなり低濃度ではあります。
しかし、歯磨き剤のフッ素は、歯を磨いている間にこすられるため付着しにくいという側面があります。そのため、欧米では歯磨きの最後に約5分間、フッ素を口腔内にとどめる習慣が推奨されています。また、一般の歯磨き剤には発泡剤が

含まれているため、泡立ちにより早めに吐き出すことでフッ素濃度が低下し、製品の表示濃度よりも実際の効果が低くなる可能性があります。
一方で、唾液の濃度は低いものの、1日24時間を通じてエナメル質に再沈着するチャンスがあります。この時間を活かすことが大切です。
そのために重要なのは、
- エナメル質を削らないこと
- エナメル質表面の汚れをしっかり落とし、リン酸やカルシウムが付着しやすい状態を保つこと
このシンプルながら重要な習慣を意識することで、フッ素を使用する以外の方法としてエナメル質の健康を維持することが可能になります。
アメリカで水道水のフッ素化が実施された目的は、虫歯(う蝕)の予防です。公衆衛生の一環として、1945年にアメリカのグランドラピッズ(ミシガン州)で初めて導入されました。フッ素化によって虫歯が減少し、歯科治療費の負担が軽減されるという医療費削減の目的もあります。
水道水中のフッ素含有率は、0.7~1.2 ppm の範囲で設定され、最大許容レベルは4.0 ppmです。これは、唾液中のリン酸やカルシウム濃度(60~170 ppm)と比べるとはるかに低い値となっています。
言い換えると、唾液中のリン酸やカルシウムの濃度は歯磨き剤のフッ素濃度と比べると低いですが、米国で認められた水道水のフッ素濃度よりは高い値であることがわかります。したがって、唾液によるエナメル質の再石灰化は、十分に現実的なメカニズムであると考えられます。
同時に、知覚過敏の主な原因としては、研磨剤の使い過ぎや、酢の物など酸性食品への配慮の欠如が挙げられます。歯磨き剤の種類や性能、生活習慣をしっかりと見直すことが大切です。