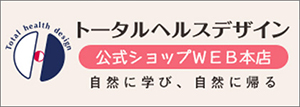私たちの健康は、体の「内側」と「外側」が絶えず影響し合っています。その中でも、口の中の環境は、私たちの生活習慣や体内環境を鋭く反映する“健康の鏡”とも言える存在です。
これまでの記事では、体液が弱アルカリ性であることの重要性や、酸性食品とアルカリ性食品の違いなどを解説してきました。今回はそれらを踏まえて、「なぜ食事を正すと口の中が健康になるのか」について、総括としてまとめていきます。
弱アルカリ性の体液が口腔環境に与える恩恵
私たちの血液や唾液、細胞の内外を満たす体液は、本来「弱アルカリ性(pH7.35〜7.45)」に保たれています。このわずかなpHのバランスが乱れるだけで、免疫力や代謝、消化、再生といった体の重要な働きに支障が出ることがわかっています。
唾液も例外ではなく、唾液が中性〜弱アルカリ性に保たれていることで、虫歯や歯周病の原因菌(ミュータンス菌やP.g菌など)の活動が抑えられます。逆に酸性に傾くと、これらの菌が活発になり、歯や歯茎のトラブルが起こりやすくなります。

食事の質が体液の質を決める
体液のpHは、遺伝ではなく「日々の生活習慣」、とくに食事の内容に大きく左右されることがわかってきました。動物性脂肪や精製糖、加工食品中心の食生活は、体を酸性に傾けやすく、免疫の低下・慢性炎症・疲労感の増加などを招きます。
一方で、野菜や果物、海藻類、豆類など、アルカリ性食品を中心とした食生活を送ることで、体液が弱アルカリ性に保たれ、口の中も良好な環境を維持しやすくなります。
善玉菌がすみやすい「土壌」をつくる
口腔内には常に数百種類の細菌が生息しています。その中には、私たちの健康を守る善玉菌(常在菌)も含まれており、この善玉菌が安定して住みやすい環境が保たれることが、健康な口腔の鍵となります。
歯磨きだけでは菌を“ゼロ”にすることはできません。大切なのは、「菌が育つ土壌」である口腔環境をいかに整えるか。そのために、体液を弱アルカリ性に保つような食事が、実は最も根本的なケアとなるのです。
まとめ:食事は最高のオーラルケア
- 食事の内容が体液のpHバランスを左右し、それが唾液の性質にも影響を与える
- 酸性体質になると、虫歯や歯周病のリスクが高まる
- アルカリ性食品を意識して摂ることで、口腔内の善玉菌が定着しやすくなる
- 健康な口腔環境は、体全体の調和とも深くつながっている
口腔ケアは、歯ブラシや歯磨き剤だけではなく、体の内側から整えていくことが、真の意味での“予防”につながります。ぜひ、毎日の食事を見直すことから始めてみてください。口から始まる健康習慣が、あなたの全身のバランスを整えていく第一歩となります。