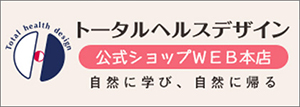私たちの体は「弱アルカリ性」に保たれているのが理想的だとよく言われます。実際、血液や体液はpH7.35〜7.45の範囲で厳密に調整されており、これが崩れると体調にさまざまな影響が出ると考えられています。
この話に関連して、「酸性食品」や「アルカリ性食品」といった分類を見聞きしたことがある方も多いと思いますが、実はここに少し誤解が含まれやすいのです。
食品の「酸性・アルカリ性」はpHではない?

多くの方が、「酸性食品=酸っぱいもの」「アルカリ性食品=苦く
てマイルドなもの」とイメージしがちですが、この分類は食品そのもののpHではなく、「体内で代謝された結果として、体にどんな影響を与えるか」を基準にしています。
つまり、「酸性食品」とは体内で酸性の代謝産物(硫酸・リン酸など)を残す食品のことで、「アルカリ性食品」とはアルカリ性の代謝産物(炭酸塩・重炭酸塩など)を残す食品を指します。
たとえばレモンや酢は酸っぱいので「酸性」だと思われがちですが、体内ではクエン酸が代謝されてアルカリ性の効果をもたらすため、「アルカリ性食品」に分類されます。
酸性食品の代表例(代謝後に体を酸性に傾けやすい)
- 肉類(特に赤身肉)
- 卵
- チーズ
- 白米・パン(精製穀物)
- 砂糖や加工食品
- コーヒー、アルコール類
これらは現代の食生活では摂取が多くなりやすいものです。
アルカリ性食品の代表例(代謝後に体をアルカリ側に保つ)
- 野菜(特に葉物や根菜)
- 果物(バナナ、レモン、メロンなど)
- 海藻類
- 大豆製品(納豆、豆腐)
- ナッツ類(アーモンドなど)
- いも類(じゃがいも、さつまいもなど)
※上記の分類は「PRAL値(Potential Renal Acid Load)」という指標を元に分類されることがあります。
バランスの崩れが健康に与える影響
体は本来、pHバランスを調整する仕組みを持っていますが、酸性食品ばかりが続くと、体は骨や筋肉を分解してアルカリ成分(カルシウムやマグネシウム)を動員して中和しようとします。これが続くと骨密度の低下や筋力低下につながることもあり、慢性的な炎症や疲労、免疫力の低下を招くと考えられています。
また、唾液や尿が酸性に傾くと、虫歯や歯周病、尿路結石のリスクも高まります。
大切なのは「pHバランスの取れた食事」
極端にすべてをアルカリ性食品にする必要はありませんが、動物性食品や加工食品が多くなりがちな現代の食生活では、意識して野菜や海藻、果物を取り入れることが重要です。
食後には口の中が一時的に酸性に傾きますが、唾液の働きや適切なケアによって中和されます。このとき、食事内容がアルカリ寄りであることが、回復をスムーズにする助けにもなるのです。
まとめ
- 食品の「酸性・アルカリ性」は、体内での代謝産物に基づく分類
- レモンや酢など、酸っぱいものでもアルカリ性食品に分類されることがある
- 酸性食品が多すぎると体が酸性に傾き、健康を害するリスクがある
- 野菜・果物・海藻などのアルカリ性食品を日々の食事に意識的に取り入れることが大切
体の内側の環境を整えることが、結果として口の中の健康にもつながります。口腔ケアだけでなく、食生活もあわせて見直すことが、善玉菌がすみやすい環境づくりの第一歩です。