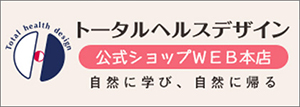本シリーズは、**現代書林刊『歯原病 ― すべての病は歯から始まる』(著:医学博士・中島 隆一)**を参考に、
口腔内の炎症が全身に及ぼす影響を、予防の視点から整理したものです。

今回は、歯原病が血管や心臓、さらには糖代謝にどのように関わっているのかを見ていきます。
■ 炎症が「血管の老化」を早める
歯ぐきの炎症が続くと、血流を通じて炎症性サイトカインが全身を巡ります。
これらは血管の内側(内皮)を刺激し、微細な傷を作ります。
そこにコレステロールなどが沈着すると、動脈硬化の始まりです。
歯原病が怖いのは、痛みや自覚症状が少ないまま、
このような「静かな炎症」が長期間続くことにあります。
結果として、血管がもろくなり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めることになるの
です。
■ 歯周病と糖尿病の「双方向の関係」
糖尿病と歯周病は、実は密接に影響し合っています。
血糖値が高い状態では、血管が傷つきやすく、歯ぐきの抵抗力も下がります。
その結果、歯周病菌が繁殖しやすくなり、炎症が悪化。
一方で、歯周病による炎症性物質が血中に放出されると、
**インスリンの働き(血糖を下げるホルモン)**が弱まり、血糖コントロールがさらに乱れます。
まさに「悪循環」です。
最近では、歯周病を治療すると血糖値が改善するケースも報告されており、
糖尿病の管理において“口腔ケア”が不可欠であることが強調されています。
■ 小さな炎症が心臓に届く
歯原病の炎症によって発生する菌や毒素が血流に乗ると、
心臓弁膜や冠動脈に到達することがあります。
特に免疫力が低下している高齢者や持病のある方では、
感染性心内膜炎などの重大な合併症につながることもあります。
つまり、歯ぐきの出血や腫れを「よくあること」と見過ごすことは、
心臓や血管を危険にさらすことにもつながるのです。
■ 歯原病の予防は「血管の若返り」
炎症を抑えるということは、血管の老化を止めることにもつながります。
そのためには、毎日の口腔ケアを刺激の少ない方法で継続することが大切です。
歯磨き粉の選択ひとつでも結果は変わります。
たとえば、弱アルカリ性で抗炎症性のある天然ミネラル成分を含む製品は、
酸化を防ぎ、血流や細胞のバランスを守る助けになります。
■ バイオペーストが目指すケア
バイオペーストは、そうした考え方から生まれた製品です。
化学的な殺菌剤に頼らず、ミネラルのイオンバランスで環境を整えることで、
細菌の繁殖や酸化を穏やかに抑え、口腔内の自然な恒常性を保ちます。
血管を守る第一歩は、口腔を守ること。
それは「老化を防ぐ」ことと同じ意味を持ちます。
■ まとめ
歯原病は、血管・心臓・糖代謝と密接に関係しています。
口の中の小さな炎症が、全身の血流や代謝のバランスを乱し、
やがて命に関わる疾患を引き起こすこともある――。
しかし逆にいえば、口腔環境を整えれば、
全身の健康を取り戻すこともできるのです。
毎日の歯磨きを“血管ケア”と考えることが、
これからの時代の新しい健康習慣になるでしょう。